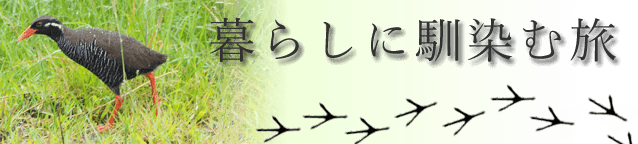オキナワシジュウガラ (沖縄四十雀) 学名:Parus minor okinawae
関西テレビ系列でやっている「僕らは奇跡でできている」という番組で主人公の高橋一生が演じる一樹が山の中で見つけた鳥はシジュウカラ(四十雀)でしたね。見た目も声もかわいい鳥です。 オキナワシジュウガラ(沖縄四十雀) 学名:Parus minor okinawae スズメ目シジュウガラ科 私が初めて写真に収めたのは国頭の山奥、ヤンバル学びの森、ヤマシンコースでした。 オキナワシジュウカラは、ツイッピーツイッピーと鳴き、留鳥として沖縄諸島に生息。スズメとほぼ同じ大きさ(全 ...

森のシャンデリア イルカンダ(ウジルカンダ) 学名:Mucuna macrocarpa
Looks like chandelier of the forest in Okinawa.Please click translation function on the upper right side of the screen. ※加筆して写真を増やし、更新しました。 イルカンダ(ウジルカンダ) 学名:Mucuna macrocarpa マメ目マメ科 蔓性植物で他の木に巻きつきながら成長します。 イルカンダは蝶が受粉を手伝うのではなく、オリイオオコウモリが蜜を吸うときに ...

ヒカゲヘゴ (日陰杪欏) 学名:Cyathea lepifera
ヒカゲヘゴ (日陰杪欏) 学名:Cyathea lepifera ヘゴ目ヘゴ科ヘゴ属 多年生のシダ植物 沖縄の至る所に生えていてこれぞ南国の雰囲気を醸し出しているヒカゲヘゴ。 大型でいかにも太古を偲ばせるが、実はヘゴ科の植物はシダ植物の中では 比較的新しく約1億年前の出現らしい。 その後地球が寒冷化して暖かい南でしか生きられなくなったとか。 丸い模様はかつての葉の痕跡(葉痕)。 やがて茶色の短い木根で覆われて見えなくなってしまいます。 ちなみにこの模様が小判に見える ...

リュウキュウコスミレ(琉球小菫) 学名:Viola yedoensis var. pseudo-japonica
リュウキュウコスミレ(琉球小菫) 学名:Viola yedoensis var. pseudo-japonica スミレ科スミレ属 くたっと首が折れているのが特徴でノジスミレの花に似ている。 沖縄本島の冬から春にかけて咲く可愛いスミレ。 東村のカフェ たちがあのお庭では白い個体も見ることができました。 始めて観察会で見たときは珍しいものだと思ったのですが、その存在に一旦目がいくようになると公園や民家など至る所で目にするようになりました。 それでも名護岳で見たものが1番 ...

リュウキュウイチゴ(琉球苺) 学名:Rubus grayanus
リュウキュウイチゴ(琉球苺) バラ科キイチゴ属 学名:Rubus grayanus 地面に向かって可憐な小ぶりの白い花が咲く。 リュウキュウバライチゴとは葉の形態が異なり、独立した一枚になっています。 冬場、花が少ない頃にリュウキュウイチゴもリュウキュウバライチゴも共に咲くので私は特にこの花たちが好きです。 ジャムにするなら沖縄のキイチゴならリュウキュウバライチゴのジャムが一番美味しいと聞いていたけど このリュウキュウイチゴが一番美味しいという意見をチラホラと見かけます。 食べた感 ...

クダモノトケイソウ(果物時計草)学名:Passiflora
クダモノトケイソウ(果物時計草) スミレ目トケイソウ科 学名:Passiflora edulis 南国の果物「パッションフルーツ」の花 花言葉の「情熱的に生きる」にぴったりの艶やかな花です。 クダモノトケイソウが属しているトケイソウは英名でパッションフラワーと呼ばれ、 この花をキリストの十字架に見立ててキリスト教を広める為に使ったと言われています。 一方、和名で時計草というように日本では3つに分かれたおしべを時計の針に見立てその花を愛でたと言われています。 花の種類も500近くあ ...

リュウキュウヒメジャノメ(琉球姫蛇目)学名:Mycalesis madjicosa
リュウキュウヒメジャノメ(琉球姫蛇目) チョウ目タテハチョウ科 学名:Mycalesis madjicosa 八重山諸島では周年、沖縄本島では3月~12月に成虫として活動。 幼虫はチガヤ、ススキなどを食べます。 リュウキュウヒメジャノメの名前の由来は羽に蛇の目(じゃのめ)の様な模様があるから。 交尾しているリュウキュウヒメジャノメ 南国特有の派手な色合いの蝶が多い沖縄の中ではかなり地味目の蝶。 名護岳と轟の滝で撮影しました。

リュウキュウミスジ(琉球三筋)学名:Neptis hylas luculenta
リュウキュウミスジ(琉球三筋) チョウ目アゲハチョウ上科タテハチョウ科 学名:Neptis hylas luculenta リュウキュウミスジは日本の本州(九州、四国を含む)のコミスジNeptis sappho intermediaとそっくりですが、 調べた所ではコミスジは西南諸島には生息しないとのこと。 ただし、台湾には生息しています。 沖縄と台湾は生き物がかなり行き来しているので迷蝶(めいちょう)でコミスジが来ていることも考えられます。 正直、素人の私にはリュウキュウミスジなの ...

ツマグロヒョウモンの雄 (褄黒豹紋) 学名:Argyreus hyperbius
ツマグロヒョウモンのメスはこちら ツマグロヒョウモンのメス ツマグロヒョウモン (褄黒豹紋) チョウ目タテハチョウ科 学名:Argyreus hyperbius 沖縄ではかなり頻繁にみかける蝶です。 これは乙羽岳(おっぱだけ)で撮影したもの。 こちらは名護岳の山頂にて撮影。幼虫はリュウキュウコスミレを食草にします。 リュウキュウコスミレ 成虫はタチアワユキセンダングサの周りでよく見かけます。 タチアワユキセンダングサ ...

オキナワルリチラシ (沖縄瑠璃散らし) 学名:Eterusia aedea
オキナワルリチラシ (沖縄瑠璃散らし) チョウ目マダラガ科 学名:Eterusia aedea 初めて名護岳に登ったときに遭遇したのがオキナワルリチラシ。 羽を広げれば金青色の鱗粉を散らしてそれはそれは綺麗です。 沖縄外にいるのはルリチラシでもっと地味な模様です。 蝶は南に行けば行くほど翅の模様が綺麗で派手になる傾向があります。 そして日本ではオキナワルリチラシは「蛾」に分類されます。 もっとも「蛾(butterfly)」と「蝶(moth )」と日本語や ...